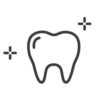みなさん、こんにちは! 茨木市彩都の歯医者さん、くになが歯科医院です。今日は「指しゃぶりはやめないといけないの?」という疑問についてお話しします。
指しゃぶりは吸指癖といい、1歳6か月健診や3歳健診で、度々相談を受けます。
この指しゃぶりは、大半の歯科医からは止めるよう指導される一方、医師からは止めなくてよいと指導されることがあり患者さまのご家族は混乱してしまうことがあると思います。
『指しゃぶりは歯並びに影響する?!』
指しゃぶりがあっても、噛み合わせに問題ない子供がいるのも事実です。
例えば、1~2歳で指しゃぶりが原因で噛み合わせに問題を起こしている場合、止めさせるように家族に指導されます。
一方、5歳を過ぎて指しゃぶりが認められる場合でも、噛み合わせに問題がないときは、注意深く経過観察を行っていきます。
『噛み合わせの問題とは?!』
噛み合わせの異常の種類としては、開咬、上顎前突、正中のずれが考えられます。
将来的に噛み合わせに問題が生じる可能性が高く、指しゃぶりを早急に止めさせるチェックポイントは次のものです。
・頭蓋の形:うつぶせ寝で細長い頭の形
・歯列の形:V字形の歯列の方が、半円形やU字形よりも危険性あり
・前歯部の噛み合わせ:開咬(歯と歯が嚙み合っていなく、すいている)
・臼歯部の噛み合わせ:交叉咬合(歯と歯が嚙み合っていなく、ずれた位置関係)
『噛み合わせ問題どうすればいいの?!』
上記の場合、3歳前後を目安に徐々に止めれるように生活指導をします。
そのころには、大人のお話も聞けるようになるので、歯科衛生士が本人と向き合って話をしていきます。
指しゃぶりは不安や緊張を和らげ、精神の安定につながるとされているので、急には止めさせなくてよいと思います。
何か夢中になれるものができると、自然と指しゃぶりは減るので、周りは焦らず待ちましょう。
就寝前の指しゃぶりは止めにくいですが、母親がしゃぶる側の手をつないで寝るように指導します。
もう一点、注意することは、指しゃぶりが止めれても、開咬している所へ、舌を入れてしまう舌突出癖に移行すると、開咬は改善しません。
ただ、幼児期は舌突出癖など習癖の対応が難しいので、学童期に入ってから積極的に取り組むようするとよいでしょう。
その際、本人が理解して、止める努力をすれば、良い結果になります。
次回は、別のテーマでお会いしましょう。それでは、健康な歯で笑顔溢れる日々をお過ごしください。
茨木市彩都の歯医者さん くになが歯科医院
茨木市彩都あさぎ2丁目1-9